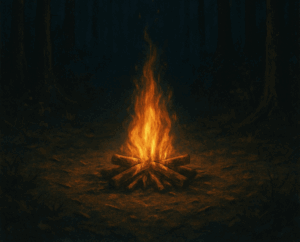傷ついたヒーラー ― もう一度旅に出る理由 ―
心理療法というものは、劇的に変化することは稀だ。
少しずつ、ゆっくりと、しかし確かに何かが動いていく。
数年前、とある青年と出会った。
彼とのケースは、今も私の中で静かに息づいている。
傷ついた彼は、何度も私を揺さぶり、失望や怒り、無力感をぶつけてきた。
私もまた迷い、悩みながら、それでも何度もこう問いかけた。
「君は、どうしていきたいの?」
私が働く児童福祉施設は、心理職と生活職員の緊密な連携によって、
子どもたちの育ちを支えている。
彼との関わりもまた、何度も転覆しそうになりながら、職員たちと力を合わせて支え続けた。
やがて彼は、少しずつ変わっていった。
他の子どもとの関係を見つめ直し、職員に助けを求めるようになっていった。
カウンセリングの中では、友人関係や家族との葛藤を語るようになり、
私との関係性を軸にしながら、「自分がどうありたいのか」を共に考えるようになった。
そこには、穏やかで、静かな時間が流れていた。
あるとき、彼はこう語ってくれた。
「最初は、河村さんもどうせ他の大人と同じだろうと思った。
でも河村さんは、どんなことを言っても怒らなかったし、
一緒に考えて、自分の言葉で問いかけてくれた。
だから、もう一度、人を信じてみようと思った。河村さんが導いてくれたように思った。」
──だが、あの頃の私は荒々しく、未熟なセラピストだった。
今なら、もう少し間をとって問いかけるだろう場面でも、
あの頃は鋭く問いを投げ、彼を“導こう”としていた。
彼が見ていたのは、随分と理想化された幻想のヒーラーである私だったのだろう。
けれど、彼が少しずつ変化する中で、
私自身の問いかけも、態度も、穏やかになっていった。
そして、彼と対話を重ねる中で、
私自身の中にある父子関係の傷つきの記憶が、繰り返し浮かび上がってきた。
彼の揺れや葛藤を受け止めながら、
私もまた、自分の中にある古い傷と静かに向き合っていたのだと思う。
スーパーバイザーとの対話や、家族とのやり取りの中で、
少しずつ私自身も癒され、
いつしか、父に対して柔らかいまなざしを向けられるようになっていた。
それは、彼との出会いが私にもたらしてくれた贈り物だった。
けれど、いつしか私は、彼に過度な期待を抱いていたのかもしれない。
彼が語ったささやかな一言を、過度に称賛してしまったり、
励ましの言葉を、普段よりも強く重ねている自分に気づいたことがあった。
「この子は乗り越えられる」「この子なら大丈夫」──
そんなふうに“信じる”という名のもとに、
私はどこかで彼を理想の傷負い人として扱っていたのかもしれない。
入れ子のように、私もまた、彼の中に“癒やされるべき存在”の象徴を見出していたのだ。
それでも関係が破断しなかったのは、
幻想を抱きつつも、最後には「それで君はどうしたいんだろう?」と問いかけ、
心理面接の主体を彼に返していたからだろう。
だが、夢はいつか終わるものだ。
退所する頃には、彼は自分の人生を切り開くための力を持つ、
立派な青年になっていた。
世の中に絶望し、委縮しながら生きていた彼とは、まるで別人のようだった。
二人の抱いた幻想は終わった。
けれどその幻想は、互いの心の中に静かに残り、
忘れ去られていくようでいて、確かにどこかに刻まれている。
心理臨床では、こういうことが起こる。
相談者が癒されているようで、
実は、セラピストが癒されている。
相談者が導かれているようで、
実は、セラピストが導かれている。
そこには、
「サービス提供者」と「受益者」、
「ヒーラー」と「傷を抱えた人」──
そんな立場や構図を越えた、
一人の人間と一人の人間の出会いがある。
そしてその過程にこそ、成長がある。
もちろん、そのバランスが崩れれば、
セラピストが相談者を利用し、搾取する構造にもなりうる。
だからこそ、心理療法はいつも、
繊細な倫理と責任の上に成り立っている。
彼との過程は、私にとっても一つの旅だった。
記録を何年かぶりに読み返し、私はいくつもの新しい発見をした。
旅を終えると、新しい旅に出たくなる。
だから、きっと私は──
もう一度、センターという名の旅を歩もうと決めたのだ。
※ 本記事は、個人の特定を避けるために複数の事例を統合・再構成し、個人情報保護に十分配慮しています。臨床的な本質を伝えるために、語りの一部には象徴的な表現や抽象化が含まれています。